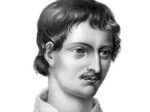もっと皆に広めたい「世界に誇る日本の研究」
- 2025/10/9
- できる人研究所

ノーベル生理学・医学賞を受賞した
坂口志文教授に続き、
京都大学の北川進特別教授が
ノーベル化学賞を受賞しました。
素晴らしいことですよね。
これでノーベル賞をとった日本人は
30人目だそうです。
本当に素晴らしいことであるのですが、
惜しむらくは、
「坂口先生の制御性T細胞」も、
北川先生の
「多孔性金属錯体」も
何のこっちゃでよくわからないこと(苦笑)
せっかく日本人の素晴らしい研究なのに、
日本人がそれを理解していないのは、
ちょっと寂しいことかもです。
なんでも「多孔性金属錯体」は、
人工的に合成する
微小な穴がたくさん空いた金属のこと。
この穴に機体を吸着することができるとか。
活性炭とは、あれ炭に空いたたくさんの隙間に、
匂いの素を閉じ込めるわけですよね。
だから防臭剤になるのですが、
これをさらに高度なレベルで行なうのが、
「多孔性金属錯体」とのこと。
まだ実用化は始まったばかりですが、
天然ガスや水素の貯蔵や運搬。
あるいはCO2を閉じ込めて、
そのままアルコールに変換してしまうような
技術も考えられているから。
ひょっとしたらこれは、
地球温暖化を救うことになるのかもしれない。
そんな期待がノーベル賞に
つながっているのでしょうね。
一方で「制御性T細胞」は、
白血球などの免疫細胞が、
身体の細胞を傷つけないよう
反応を抑える細胞。
これ、じつは子供たちにはお馴染みで、
『はたらく細胞』の中に
しっかりと描かれているそうです。
病原菌と戦う細胞たちの
サポート役のようになるのでしょうね。
こういうのが増えていけば、
サイエンスに興味を持つ子どもたちも
多くなるかも。
日本のノーベル賞30人は国にすれば世界5位ですが、
大学にすると京都大学がやっと14位になるくらい。
個々の能力はともかく
「研究の場」としては、
日本はまだまだなのが現実のようです。