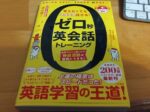昨日の夜は、リモートで
「賢者の会」を開催しました。
テーマは「本を読むこと」。
文章を書き、本の出版を目指す皆さんが、
あらためて本との出会いや、その価値について考え、
文章にした。
なかなか素敵なエッセイが集まりました!
その中で参加者のかや崎さん、カールさんから
提唱されたのが、
「本は五感で感じるもの」だということ。
本屋さんの雰囲気、書庫の香り、
紙の質感に、装丁の手触り、
すべてを総じたものが
「本の楽しさ」になっているわけです。
その価値を伝える場を、
私たちは提供していきたいですね。
「本作りはムダを排除するのでなく、
むしろ取り込んでいくもの」……京極夏彦
長くなりますが、今回、
私が執筆した文章を掲載します。
◇◇◇◇◇
・本屋さんで出遭えるもの……我が心の中のサツマヤ 夏川賀央
197X年春、東京港区……目黒通りが国道1号線と交わる近く、結婚式場として有名な八芳園の向かい側近くに、その書店はあった。
サツマヤ書店、中年の男性兄弟3人が運営している小さな書店。店主たちが鹿児島出身かどうかは知らない。その昔は商店街に必ず1軒はあった、ごく普通の小さな書店である。
小さな書店だが、3人兄弟が本の注文配達を引き受けていることもあり、蔵書数はやたら多い。店は5メートルくらいの通路が2本あるだけだが、片方はお客さんが本を買う店舗で、壁一面、6段くらいの高さまで本棚が備えられている。上のほうはもちろん、梯子でないと取れない。
一番奥にあるレジで分けられた、片方の通路側も同じような構造だが、普通の本屋さんと違うのは、こちらが完全に本の保管スペースになっていること。
だから、お客さんは入れない……はずだが? えっ?
よく見ると、小さな椅子に男の子が1人座っている。まだ小学校低学年くらいの年齢だろうか……。ただ、読んでいる本は、マニアックな戦闘機の本らしい。
「おじさん、ごめんなさい。もう夕方だし、帰るよ」
「まだ早いんじゃない。お母さん、帰ってないんだろ? まだ読んでていいよ」
「いいの? じゃあ、もう少し……。この本を読んじゃったらね」
少し茶色っぽい髪に、小太りの体型。弱虫ですぐ泣くせいか、どこに行っても仲間はずれになってしまう少年。父親は仕事でほとんど家にいない。母親は小さな妹をつれて、どこかに毎度、出かけている。
近所のお友達の家でもいじめられるし、図書館に行ってもいじめっ子がいる。親に相談すると、「マンガでも買って読みなさい」と言われ、サツマヤ屋書店に行ってみる。でも、何を読んだらいいのか……。
「いいよ! 好きなだけここで選んでも。その辺に子供用の本はあるから! ごめんね、構ってはあげられないけど、椅子を持ってくるから……。そこはお客さん、来ないから、好きなだけいていいよ」
今、思うと「なんとなく可哀想な子供なんだろうな」と、本屋さんは同情したのだろうか。サツマヤの書庫スペースは、いつしかその子の読書室になってしまった。
小さな書店ではあったが、世界を知らない子供にとって、そこはまさに知の宝庫だった。
子供用の絵本は当然、読み尽くし、漫画はもちろん、写真の多い図鑑や、ビジュアル雑誌は読み尽くす。マンガも子供向けから大人向けまで、片っ端から読む。ハヤカワ文庫に、創元推理、角川文庫はもちろん、岩波新書やら中公新書のような教養書まで。当時はまったく規制のゆるかったエログロやら残虐描写やらも、あらかた小学校低学年で卒業してしまった……。
やがて少年は中学を卒業し、高校へ。
いつしかサツマヤさんには行かなくなったが、知識を求めて本屋さんに行く習慣は変わらない。青年になった彼は、「読んだ本の中で一番面白かった分野」ということで、専攻に古代史を選んだが、それも物足りなくなって。自分が本を作る側に回ることにした。
そしていくつかの出版社を経て、本の書き手になる……。
こんなふうにして、「本に育てられた雑学作家」が出来上がったわけだ。
すでにサツマヤさんは世になく、街から本屋さん自体が消えている。だいたい知識の宝庫も未知なる世界も、すでにポケットサイズの薄い機器に収まって、皆が日常で携えているのである。
もはや知識を引き出すのはたくさんの機能の1つとなり、それほど重要視はされていない。今の時代に、私のような「雑学作家」になる道は、たぶん難しいだろう。というか、この効率化した時代に、雑学作家など、たぶん必要ない。
でも、それではなにか面白くない気がする……。
冒険者に未知なる知識を授けたり、持っている知識をもって問題解決をする人。たぶん、これは雑学作家の進化形態で、ファンタジーでは「賢者」と呼ばれる人間だと思う。
私は自分で作った電子出版のサイトに「賢者の書店」の名づけ、そのビジネスが失敗した現在も、仲間を集って、知識と出逢える場をつくりたいと模索している。果たして、かのサツマヤのような場所を、再び世の中に作り出せるのか? まだまだ自分の冒険は続きそうである。