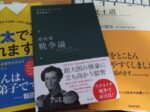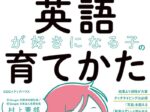源内? 南畝? 「土用の丑のウナギ」の秘密
- 2025/8/1
- できる人研究所

ついに8月になりました。
津波に続き、列島には台風が近づいているとのこと。
少し今日は涼しい感じもありますが、
注意して過ごしましょう!
7月末の31日は、この夏で2回目になる
「土曜の丑の日」でした。
私もなんとか、スーパーで買ったウナギを
食することができました。
ちょっとタレが足りなかったのが残念でしたが(苦笑)
ありがたいですよね。本当に。
今年の「土用の丑の日」は、ちょっと例年と違う。
というのも、江戸時代に
この「キャッチ」を定着させたと言われる人物、
平賀源内さんか、あるいは大田南畝さんか
……ですが、
いずれも蔦屋重三郎さんの、関係者だった人物です。
すぐれた文化人であり、作家やクリエイターとして
皆から認知されていた。
だからこそ、現代までもウナギを売り続ける
強力な「コピーライト伝説」が生まれたのですが、
江戸随一のプロデューサーは
両者をちゃんと活用していたんですね。
平賀源内と「土用の丑のウナギ」の話は、
以前にもブログに書きました。
科学者であり、発明家であり、興行士であり、
作家や戯作者としてもしられた平賀源内さん。
その本職は今でいう
「コンサルタント」のような仕事でしたが、
鰻屋さんの売り上げを伸ばす方法を頼まれて、
思いついたのが、
「夏バテに鰻がいい」
だから「土用の丑の日に食べようよ」という
売り文句です。
それがいつのまにか定着し、
現代まで当たり前の慣習になってしまった
……というもの。
そういえば蔦重の最初の本で序文を書き、
「耕書堂」という屋号を考えたのも
源内さんでした。
ヒットの原動力として語られるのも
当然かもしれませんね。
ただ、ドラマでご存知の通り、
牢獄で早くに亡くなっている源内さん。
そんな鰻屋にかかわった記録は
どこにもありません。
代わりに言われるのは、
ウナギについての狂歌を多く残している
狂歌師の大田南畝さんですね。
こちらも蔦重のドラマに登場していますが、
教養あるエリートであり、
文芸評論家としても知られた南畝さん。
蔦重を狂歌の道に誘った人物でしたが、
その本職は幕府の役人です。
じつは下級武士から学問を学ぶことで
地道に出世してきた南畝さん、
一時は蔦重たちが幕府と対立したことで
不遇を味わいますが、
さらに学問を追求し、自らの地位を高めた上で
「蜀山人」というペンネームで
蔦重なき時代の文壇に復活します。
彼が「土用の丑」のキャッチに携わった
証拠もないのですが、
長い人生の功績として語られる
伝説になったのかもしれません。
いずれにしろ、
「土用の丑の日にウナギ」が、
これが意図的なセールス文句だと
江戸時代から広く知られていたのは面白いですよね。
それでも庶民はこの日に、
騙されているとわかってウナギを食べ続けた。
こういう考え方が「粋」なのではないでしょうか。