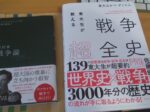「月見団子」の仕事術
- 2025/10/7
- できる人研究所

画像は東急線目黒駅の
改札前で売っていた巨大な団子!
美味しそうだったのでつい
買ってしまったのですが、
10月6日は「十五夜」でしたね。
中秋の名月……は、
天気が悪く見えなかったのですが、
お団子はとりあえず、
食べることができたわけです。
でも、6日なのになぜ、「15夜」なのか。
それは月の満ち欠けを土台にした太陰暦である
「旧暦」に合わせているからですね。
さすがに新暦の8月15日にはしない。
中国に「中秋節」という祭事があり、
満月に近い、美しい月が出る日が多い
……ということで、宴を開く習慣があった。
それを遊ぶのがほぼ仕事だった
平安貴族が採用したんですね。
同時に、収穫の時期と重なるから、
実ったお米で団子をつくり、
月に見立てる習慣ができた。
さらに江戸では、
吉原の遊女さんがやっぱり宴を開き、
15日だけでなく
「13夜(いざよい)」も来てね……と
お月見をすべき日がどんどん増えていった。
ようは営業じゃないか……。
いずれにしろ、
収穫物をお月様に供えるのが正しい作法なので、
やっぱり日本人は「団子」が相応しいし、
米が不足した今年は
とくにお祝いしたい。
といって箱の裏の原材料表示を見たら、
「アメリカ産米を使用」と
しっかり書いてありました(苦笑)
正直、月見といえば、
今の日本ではこっちですが、

お米より卵のほうが、
一般的なのだろうか?
これはこれで収穫をお祝いし、
前のようにもっと安く買える
世の中になってほしいですね!