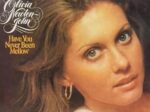- Home
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門
- 幻の「チーズ和食」とは?
幻の「チーズ和食」とは?
- 2025/11/13
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門

少し前の11月11日といえば、
1が並ぶということで、
いろんな記念日になっていました。
ポッキーの日だとか、煙突の日だとか、
もやしの日だとか、シャープペンの日だとか、
チンアナゴの日だとか、足が4本ということで
恋人たちの日だとか。
そんな中で、1の並びとは関係なく、
この日は「チーズの日」にもなっていました。
飛鳥時代の700年のちょうどこの頃、
日本のリーダーだった文武天皇が
「チーズの製造を命じた」という
記録があるのだそうですね。
でも、チーズ?
それって洋食ではないのか?
正しくは「蘇」という乳製品だそうですが、
チーズに似たものであって、
製品は明らかになっていません。
ただ、明治以後の日本に
乳製品が入ってくるずっと前、
古代の日本で「チーズに似たもの」が
食されていたのは事実のようですね。
じつはチーズというのは、
日本の歴史が始まるずっと以前から
アジアやヨーロッパでは民衆が食べてきた
古い食べ物です。
牛がいない地方でも、ヤギや羊で作っていたし、
瀕死のお釈迦さまを救ったのも
そういえばミルク粥のような食べ物でした。
乳製品は小麦と同じくらい、
人類にとって馴染みの深い
食べ物だったんですね。
仏教の伝来ともに、
中国や朝鮮半島を経由して、
日本にも乳製品はやってきます。
おそらくは牛も一緒にやってきていたのでしょうね。
それで比較的長持ちする保存食として、
「蘇=チーズのようなもの」は、
貴重な食材として推奨された。
文武天皇は全国の特産品として、
これを普及させようとしていたし、
平安時代になっても貴族たちは、
デザートのような扱いで、食べていたらしい。
ところが鎌倉時代になって武士が台頭し、
いつのまにか日本のチーズ文化は
失われてしまいました。
豊富なバリエーションで
私たちが誇りにしている「和食」ですが、
こんなふうに時代の変化で
ボツになっている料理もあるんですね。
ちなみに画像が、wikiにあった
再現された「蘇」。
コロナの頃は再現しようという
試みがあったようですが、
ちょっと食べてみたい気はしますね。