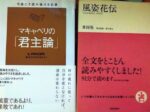お盆のころの思い出は
- 2025/7/13
- できる人研究所

7月13日は、旧暦での
お盆の初日だそうですね。
13日から16日までをかけて、
迎え日を炊いて先祖の霊を招いたり、
ナスやキュウリの供物でもてなしたり、
あるいは盆踊りをしたり
花火をしたり……ですが、
どっちかといえば8月の13日から
16日にやる人のほうが多いのではないか?
ほとんどは新暦に合わせるようになった
「お盆」の行事。
なぜ8月にやるようになったかといえば、
大きな理由は夏休みだから。
皆が集まりやすいということで、
自然と8月にすることが多くなった。
そんなのでいいのかと思いますが、
そもそも夏にお盆をやるようになったのも、
一番やりやすかったから、という話があります。
逆に考えれば、
皆が集まれるときに、先祖の霊をもてなすことが
絶対に必要だと、日本人は考えていたわけです。
だから夏休みには、
「お盆の行事」をするのが必然。
私も記憶があります。
長野県にある母方のおばあちゃんの家に行ったとき、
送り火を焚き、
「じいちゃん、ばあちゃん、このあかりに
おでやれ、おでやれ」
なんていって、山の上にあるお墓参りをした。
田んぼのある道を、提灯を持ちながら歩き、
田舎の家に帰ったのを
とても懐かしく覚えています。
いま、じつは、そのお墓はといえば、
なくなってしまったんですね。
本来なら、亡きおばあちゃんも、
そこで眠っているはずのお墓。
でも、母方の親戚がお墓じまいをしたので、
もうおばあちゃんの墓も、
母方の祖先の墓もない。
同時にお盆の行事もしなくなり、
親戚同士の付き合いもなくなり、
おばあちゃんを迎えることはずっとできずにいる……。
それはあまりよくないですよね。
本来はお墓のあるなしに関係なく、
霊魂を迎える行事として発展してきたお盆。
ならば本当は「墓文化」は薄れてきた時代にこそ、
行事としては再考されるべきなのかもしれない。
そう思っていると、スーパーにじつは
割り箸で足をつけたナスやキュウリや、
「迎え火」のセット一式が売っていることに気づいたら。
お墓参りをしなくて、
「お盆」はちゃんと、
やってあげたいところですね。